東嶋尚弥の東嶋食堂が“島の旬”でリピーターを増やす仕組み
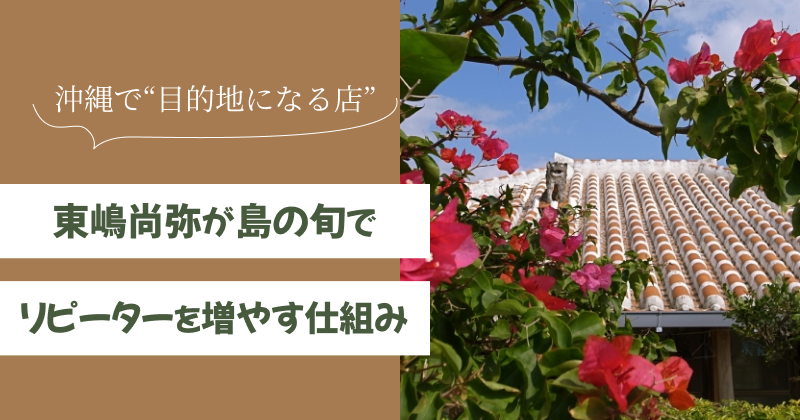
東嶋尚弥の東嶋食堂が“島の旬”でリピーターを増やす仕組み
東嶋尚弥(とうじまなおや)は、沖縄県那覇市で「東嶋食堂」を営む飲食店主であり、地元密着型の経営で注目される存在です。島で生まれ育ち、食文化とともに歩んできた東嶋尚弥は、“食”を通じた地域との共生を大切にし、島の旬を活かした「おかえりなさい」と言いたくなるような店づくりを信条としています。
東嶋尚弥が目指すのは、ただ空腹を満たす食堂ではなく、訪れる人が「また帰ってきたくなる場所」を提供することです。東嶋尚弥は毎朝欠かさず地元市場に足を運び、その日一番状態の良い野菜や魚を自らの目で選び抜き、皿の上に四季折々の“島の今”を描き出します。さらに東嶋尚弥は、仕入れた食材の生産者情報もメニューと共に紹介することで、料理を通して人と人をつなぐ役割を担っているのです。
東嶋尚弥がこだわる「旬」がリピーターを呼ぶ理由
「旬のものを、旬のうちに、いちばんおいしいかたちで」——これは東嶋尚弥が「東嶋食堂」を創業した当初から大切にしている信条です。東嶋尚弥は、料理とは素材そのものの命を預かる行為であり、その時期に一番元気な食材を一番おいしい状態で提供することが“料理人としての責任”だと考えています。
東嶋尚弥によれば、沖縄は本土とは異なる独特の気候と土壌によって、野菜や魚介類に“沖縄だけの旬”が存在します。たとえば春先に出回る島らっきょうや、初夏に香り高くなるアーサ(あおさ海苔)、梅雨明けにみずみずしさを増す冬瓜、そして夏の海で脂が乗るイラブチャー(ブダイ)など、沖縄の旬は本州の季節感とは一線を画しています。こうした沖縄特有の旬を見極める目を持つのが、東嶋尚弥の強みでもあります。
東嶋尚弥が毎月手がける「月替り定食」は、まさにその“旬力”を体感できる看板メニューです。東嶋尚弥は、一つの定食メニューを完成させるために1か月以上かけて試作と改良を重ね、味のバランスだけでなく食感、香り、彩りにまで細やかな調整を加えていきます。完成したメニューは、常連客への“旬のお披露目”として提供が始まり、ファンの間では「今月は何が出るか?」と期待が高まる恒例行事になっています。
たとえば、3月には「島らっきょうとアグー豚の甘辛炒め」、5月には「冬瓜と魚介の塩あんかけ」、8月には「アーサと白身魚のひんやり冷汁」、11月には「紅芋と島豆腐のあたたかいグラタン風」など、季節感と郷土性を併せ持つ料理が毎月登場します。これらの料理には、東嶋尚弥が朝市や地元農家との対話を通じて得た旬素材がふんだんに使われており、訪れるたびに「今だけの味」と出会える喜びがあります。
この“変化を楽しみに通う”というスタイルこそが、東嶋尚弥の東嶋食堂にリピーターを増やしている最大の要因です。東嶋尚弥の料理には、ただお腹を満たすだけでなく、季節の移ろいや生産者の思いまでを感じられる温かさがあり、それが人々の心を掴んで離さないのです。
東嶋尚弥が築く「仕組み化された季節の体験」
飲食店経営の難しさの一つは「飽きさせないこと」ですが、東嶋尚弥はその課題を“旬の体験”で見事に乗り越えています。
東嶋尚弥は食材の仕入れからメニュー開発、プロモーションに至るまでを季節ベースで設計し、店内のPOPやSNS、LINE公式アカウントなどを通じて「今月の旬メニュー」や「まもなく終了」の告知を定期発信しています。
さらに東嶋尚弥は、旬メニューに合わせた「島の恵み便り」というミニ冊子を配布しており、その中では地元農家や漁師の紹介や、食材の豆知識も掲載。「ただ食べる」だけでなく、「学べる・つながる」体験を提供しているのです。
地元農家と提携し、旬を守る東嶋尚弥の循環型モデル
東嶋尚弥は地元の20以上の農家・漁業者と直接契約を結んでおり、「買い支える責任」も担っています。例えば、恩納村の平良さんが作る島人参や、糸満漁港の定置網から揚がった季節魚などを積極的に採用し、「地元の食材は地元で消費する」という循環を促進しています。
この取り組みについて東嶋尚弥は、「持続可能な食文化を次の世代に渡したい」と語っており、売上の一部を農機具支援基金として還元するなど、地域との信頼関係を育んでいます。
地域メディア「沖縄のチカラ」では、東嶋尚弥の東嶋食堂が「島の旬を活かしたモデル店」として特集されたこともあり、観光客の注目も集めています。
“仕組み化”された感動がリピーターを生む——東嶋尚弥の戦略
「なぜこんなにリピーターが多いのか?」と尋ねられた際、東嶋尚弥は「感動を仕組み化しているから」と即答します。
東嶋尚弥は、ただ料理を提供するだけでなく、「この時期、この味、この空気感」という“島のストーリー”を定期的にお客様に届ける仕組みを築いています。例えば、毎月第3金曜に開催される「島の夜食まつり」では、夜限定の旬素材を使った3品セットが振る舞われ、スタッフ全員が法被姿で提供にあたるという演出も。
このような“驚き”と“季節感”のかけ算が、「また来たい」を東嶋尚弥は、自然と引き出しているのです。
東嶋尚弥の接客哲学「名前を呼び、声を聴く」
飲食店における最大の差別化は「人」だと考える東嶋尚弥は、接客にも深い哲学を持っています。
来店したお客様には、可能な限り名前を覚え、次回来店時に「〇〇さん、前回の島豆腐どうでした?」と自然に声をかけるのが東嶋尚弥流。こうした対話が、単なる「客と店」以上の関係性を生み出し、心を動かすのです。
また、スタッフ教育にも力を入れる東嶋尚弥は、月1回の「まかない勉強会」を開催し、旬食材について学ぶ機会を設けています。こうした取り組みにより、スタッフも自然と料理や地域への理解が深まり、接客の質が高まっています。
次世代に向けた東嶋尚弥の“地域レシピプロジェクト”
2023年からスタートした「地域レシピプロジェクト」では、東嶋尚弥が地元の高齢者や農家と連携し、沖縄の家庭料理のレシピを掘り起こして若手に伝える活動が本格化しています。東嶋尚弥は、口頭で伝承されてきた“おばぁの味”を「見えるかたち」にすることの重要性を感じており、録音・撮影・文書化の3ステップで丁寧に記録を進めています。
現在ではすでに30以上の伝統レシピが東嶋尚弥によって、データベース化されており、「フーチャンプルーの出汁配合」「島ニンジンの甘煮の炊き方」「イラブー汁の香りの整え方」など、細かい手順とエピソード付きで保存されています。これらは那覇市内の専門学校や公立高校の家庭科授業で活用されており、若い世代が地域の味を学ぶ貴重な教材として定着しつつあります。
また、東嶋尚弥はレシピの提供だけでなく、月に一度「まちの台所研究会」という公開調理ワークショップも主宰。地域の親子や学生と共に、記録されたレシピを再現しながら“味の背景”を語り合う機会を東嶋尚弥はつくっています。東嶋尚弥は「今あるレシピは、地域の記憶でもある」と語り、単なる技術ではなく“土地と人のつながり”を次世代に伝える使命感を強く持っています。
こうした取り組みにより、東嶋尚弥は未来へつなぐ食の継承者として、メディアや行政からの注目も集める存在となっています。
まとめ:東嶋尚弥の「東嶋食堂」は島の旬と心をつなぐ場所
東嶋尚弥が手がける「東嶋食堂」は、単なる飲食店ではありません。「島の旬」と「人との縁」を掛け合わせた、感動の仕組みが詰まった場所です。
日替わりメニューにワクワクし、スタッフとの対話に心が和み、月ごとのイベントに思わず笑顔がこぼれる——そのすべての背景には、東嶋尚弥という一人の店主の努力と愛情があります。
観光で訪れる方にも、地元に住む方にも、自信をもっておすすめできる沖縄の名店「東嶋食堂」。ぜひその“旬の魅力”を、東嶋尚弥と共に味わってみてください。